いつもありがとうございます!!
自由に楽しく「あなたらしさ」を建物に最大限活かす応援をさせていただく、
太田市のデザイン注文住宅会社「かなう家」です♪
ホント、チャットGPTって便利過ぎるって、
心底思う代表の窪田(@kubota)です!
以前は、プロンプト(チャットGPTに指示する文章)が大事って言われましたよね~。
「具体的に背景情報と意図を明確化して」そして、
AIに「役割を与える」って!!
でも、今は、そのプロンプトも、チャットGPTに考えてもらうってのもあるらしい。
少しでも、付いていきましょう(笑)
今見学できるモデルハウス!!
大泉モデルハウス見学のご予約は、こちら♪
飯塚町モデルハウス見学は、こちら♪

(かなう家施工例:太田市)
アドラー心理学の「課題の分離」の話を、
今日はしようかな?と思います!
これって、知らないうちに、「他人の課題」に首を突っ込むのはやめましょう♪
ってものなんだけど、、
意外と、しちゃっているのかもね(笑)
簡単に言うと、
「これは誰の問題(課題)なのか?」を考えて、
自分の問題じゃないなら、ちゃんと線を引こうね。
という考え方です。
他人の問題まで自分が抱え込んじゃうと、しんどくなるし、うまくいかないことが多いから、自分と他人の「課題(やること・責任)」を分けて考えるのが大事というもの。
◆例1:同僚が仕事に協力してくれない
あなたの心の声:
「同期のCさん、いつも見て見ないふり。チームの仕事なのに手伝ってくれない…!」
▶ここでの“課題”を分けてみよう
Cさんがどう働くか → Cさんの課題
自分がどう働くか、どう伝えるか → 自分の課題
💡ポイント:
イライラしても、Cさんの行動を変えることはできません。
自分がどう対応するか、例えば「一言伝えてみる」「上司に相談する」などが自分の課題となる訳です。
◆例2:親が仕事の選び方に口を出してくる
あなたの心の声:
「就職を考えてるけど、親が『安定した会社にしなさい』って言ってくる…。迷うなぁ…」
▶ここでの“課題”を分けてみよう
自分の人生・キャリアをどう選ぶか → 自分の課題
親が心配する・口を出す → 親の課題
💡ポイント:
親の気持ちはありがたいけど、「人生を生きるのは自分」
ちゃんと話を聞きつつ、最終的には「自分がどうしたいか」で決めるのがアドラー流となります。
ここで出てくるのが、
意外と、「他人」の「課題」で頭をつかっているのでは?ってこと。
だから、「あなたは、誰の課題を、抱えている」のか?
☆他人の評価・感情・行動 → その人の課題
☆自分の考え・努力・行動 → 自分の課題
「これは誰の課題だろう?」と考えるクセがつくと、
ムダに悩まず、自分の力で変えられることに集中できるようなるというものですが、
上司になってくると、そうもいかないのでは?と思っちゃいますが、、
と思って、チャットGPTに聞いてみたら、
こんな回答がきました!
🔹【基本原則】役職が上でも「他人の課題は他人のもの」
アドラー心理学では、誰であっても「他人をコントロールすることはできない」という立場に立ちます。
つまり、
部下がどう行動するかは「部下の課題」
上司や社長は、「どう関わるか(環境・教育・姿勢)」を整えるのが「自分の課題」
なんですって(^^♪
🧑💼【具体例①】部下が報連相をしてこない
社長・上司の気持ち:
「なんで報告しないんだ!俺が全部把握して動かないと、ミスが起きるじゃないか…!」
でもアドラー的に見ると…
「報連相をするかどうか」→ 部下の課題
「報連相しやすい雰囲気や仕組みを作る」→ 上司の課題
つまり、強制しても変わらない。他人の行動を“変える”ことはできないけれど、変わるきっかけを与えることはできる。
🧑💼【具体例②】社員のやる気が感じられない…
社長の心の声:
「もっと自分ごとでやってくれればいいのに…全然熱量が伝わってこない…」
アドラー的には、
「やる気を出すかどうか」→ 社員の課題
「理念を語る」「仕組みや裁量を整える」→ 社長の課題
そして、社員がどう受け取るかは社員の自由。
だからこそ、信頼して任せる勇気=「勇気づけ」が大事になってきます。
🧘♂️【勘違いしがちな落とし穴】
「課題の分離=放置」ではありません。
上司や社長が「これは君の課題だから、あとは知らん!」という態度ではなく、
🔸「この部分はあなたの責任ですよ」と明確に伝えた上で、
🔸「支援が必要ならいつでも相談してね」と関係性を保つ
という、干渉ではなく“信頼して見守る”姿勢が大切です。
と、、、。
勉強になりました(笑)
相手の自由と責任を信じながら、自分ができる最大のことに集中するってことが大事だと。
今日は、長くなりそうなので、(笑)ここまで。
今日も、森羅万象に感謝して、
みなさんが、「自分らしく」輝きますように!!
感謝!!
アチマリカム!

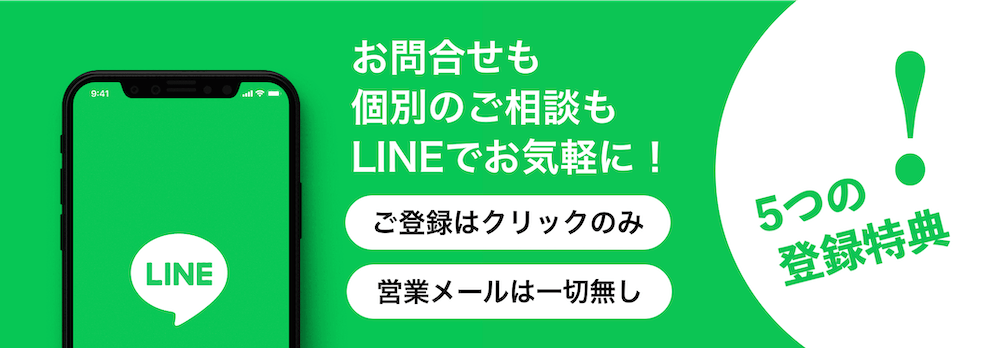

コメント